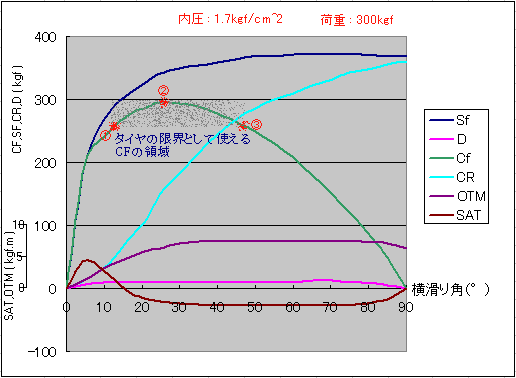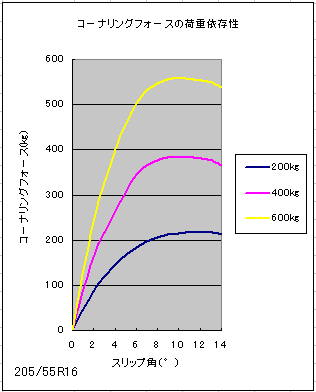|
ここでタイヤを使う為の効率について少し書いてみたいと思います。 |
| まずは上記の図を見て下さい。 上記のグラフは、y軸をタイヤが発揮する(またはタイヤに懸かる)力を示しています。 x軸はタイヤの進行方向に対する横滑り角です。身近でわかりやすく言ってしまえば「フロントタイヤ切れ角」になるのでしょうか。 上記の「CF」が「コーナリングフォース」のグラフで、この「CF」がタイヤの向きを変える力だと思ってもらえば良いでしょう。 灰色で網掛けをしたところが「イメージ」ですが、タイヤの限界として使えるコーナリングフォースの領域です。「③」を越えるとタイヤが「ギャー」と鳴いて流れ出す所です。 ※上の図はイメージですので”本当の”「使える横滑り角」の領域はもっと狭いことにご注意下さい。 サーキットやカートでタイムアタックをされたことがある方は経験があるかもしれませんが、「ちょっと軽めに行こう」と思って走ると目標に近いタイムが出て、「よーし、気合いを入れてもう一発!」と走ってみるとタイムが逆に落ち込んでしまうことがあります。 これは軽く走った時には「①」に近いところを使って走っているのに対し、気合いを入れた時にはオーバースピード等で「③」の領域を越えてしまっているからです。 何故「①」の領域を使った方が速いのでしょうか? それは「CR(コーナリング抵抗)」が「③」の領域に比べ、「①」の領域の方が低いからです。「コーナリング抵抗が低い」ということはそれだけタイヤが転がりやすい、ひいてはパワーが路面に伝わり易いことを表します。 データを取ってみるとフォーミュラドライバーなどの一流選手は「①」の領域に近いところを使って走っているそうです。 ちょっとタイヤの使い方を考えてみませんか?(^-^) |